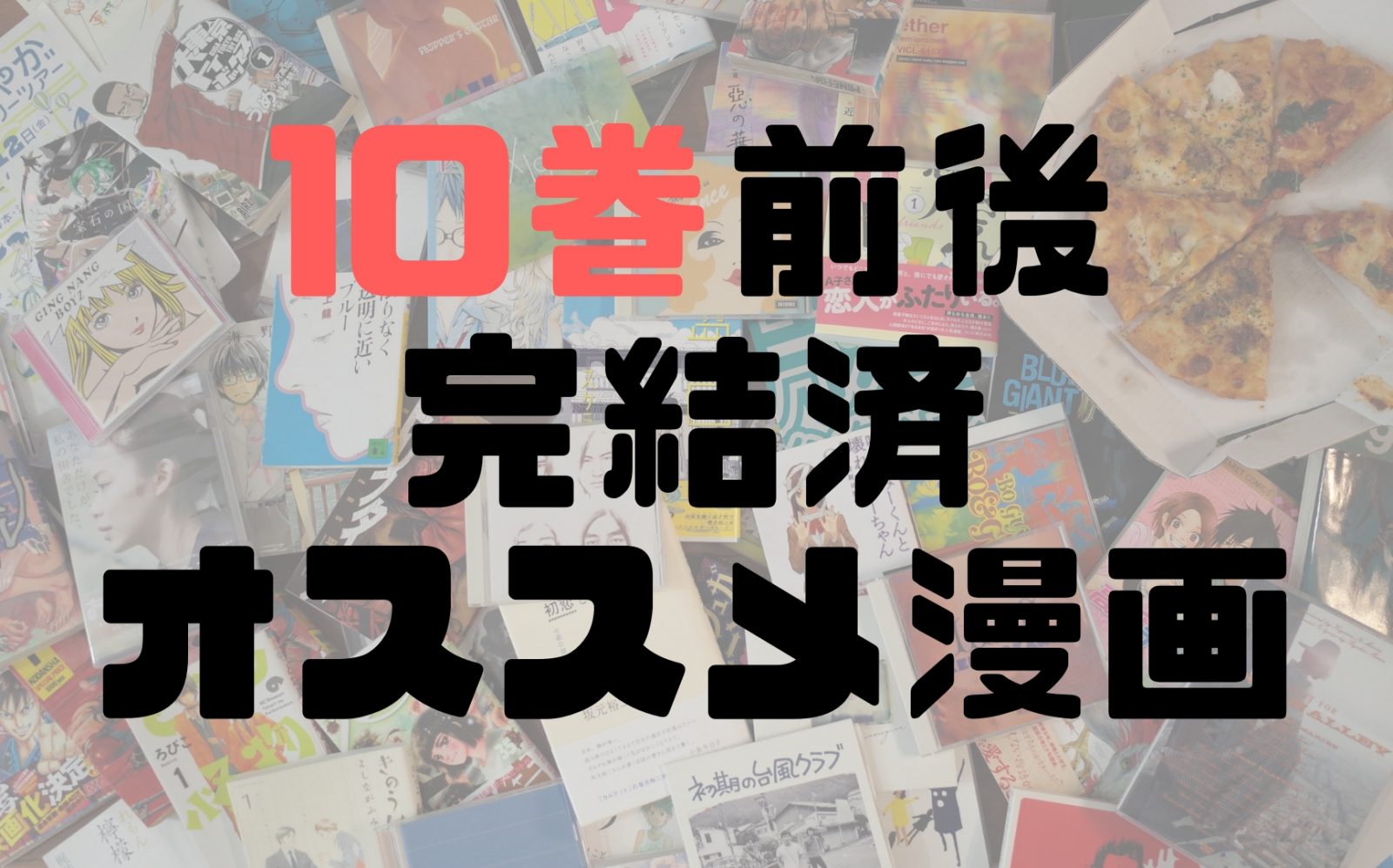西尾維新『めだかボックス』の名物キャラクター、安心院なじみはこう仰られている。

なるほど、全てが一概にこの名言に即す訳ではないが、確かに10巻前後で完結を迎える漫画には名作が多い。短すぎても読み応えがないし、長すぎるとなかなか手を出しづらい。10巻という長さは、物語として実にちょうど良いベストな長さなのだ。
となればまとめよう。古今東西の漫画を読み漁る僕がオススメする、10巻前後で完結するオススメの漫画たちを!
僕のオールタイムベストはこちらをどうぞ!
[nlink url=”https://hannbunnko.com/archives/1750″]
水上悟志『惑星のさみだれ』:10巻
最高。ストーリー、キャラクター、伏線、バトルシーン、世界観、イラストetc…その全てが最高レベルで構築された圧倒的名作。バトル要素あり、ラブコメ要素あり、友情要素あり、人情モノ要素あり。とにかく10巻というコンパクトなボリュームながら、練り込まれたストーリーの密度にただただ圧倒される。面白すぎて10巻なんてすぐ読み終えてしまうのだけれども、読後の満足感は10巻のそれではない。
あらすじなんて語ったところで大して意味が無いからとにかくまずは読んでほしい。
10巻完結でこれを超える作品は出てこないんじゃないだろうか。
和月伸宏 『武装錬金』:10巻
『武装錬金』を読んだ人と読んでない人の間には驚くほど明確な差がある。特に男子。だって、これほどまでに厨二心をくすぐる作品って他にはない。
突撃槍[ランス]の武装錬金、「サンライトハート」
処刑鎌[デスサイズ]の武装錬金、「バルキリースカート」
焼夷弾[ナパーム]の武装錬金、「ブレイズオブグローリー」
厨二病の津波みたいなネーミングセンスが最高だ。いくつになっても読み返したい最高にアツいジャンプ漫画です。ちなみに僕がイチオシは戦輪[チャクラム]の武装錬金、「モーターギア」でした。
石塚真一『BLUE GIANT』:10巻
SUPREMEを加味せず、日本編だけで考えるとぴったり10巻で完結している『BLUE GIANT』。最早この作品を知らない人はいないだろうけれども、主人公・大の成長と躍進、そして成功と挫折を超高密度に描き切った最高のジャズ漫画で、やはりこれも10巻で完結を迎えたところに意味のある作品。この10巻を読む中でどれだけ感情を揺さぶられた事か。
この作品が捻出したモチベーションの総量は、テン年代カルチャーの中で最大なんじゃないだろうか?
うめ『大東京トイボックス』:10巻
読んでる人にほとんど出会った事がない不世出の大傑作。
ゲームクリエイターの話で、モノ作りに対する情熱、こだわり、やり甲斐。大人になった僕らが忘れてしまったものが、この作品には詰まっている。僕はモチベーションの低下を感じたらすぐにこれを読んで回復します。気になったらこの記事で。
[nlink url=”https://hannbunnko.com/archives/3525″]
岩明均『寄生獣』:10巻
こちらも言わずと知れた名作。
今更深く語ることはないけれども、デビルマン→寄生獣という流れを継いだ作品が現代においてもとにかく無数にある。テーマとしては「地球、人間、環境問題、愛」といったところだろうけど、その濃密なテーマが10巻の中に凝縮されている。無駄なシーンなんて一切ないし、必殺技とか一個も出てこない。キャラクター一人一人の描き方も秀逸だし、敵味方という概念はあれどそれを公平に描き切るとこが最高。
古典作品として漫画好きは通っておいた方がいい名作でしょう。
平野耕太『HELLSING』:10巻
ヒラコーの原点にして、今もなお根強い熱狂的なファンの多い大傑作。
20世紀末のイギリスを舞台とした、吸血鬼と人間による戦いを描いた作品。何がいいってひたすらにハードボイルドなキャラクター達である。敵味方共に良キャラしかいないし、ヒラコー節とも呼ばれる癖のあるセリフ回しがとにかくカッコいい。
ヒラコー作品は絵も癖が強く、セリフも相まって世界観がとんでも無いことになっているのが特徴。そしてそれが故にハマるとものすごい没頭してしまう。ページをめくる手が止まらず、10巻なんてあっという間に読み終えてしまうし、読後感の強さもまたクセになるんだよなぁ。
大須賀めぐみ『魔王 JUVENILE REMIX』:10巻
伊坂幸太郎『グラスホッパー』と『魔王』を大胆にリミックスし、コミカライズした作品。ベースは原作だけれども、かなり大胆なリミックスがされているのでストーリーはほぼほぼオリジナルだと思って差し支えない。(きちんと伊坂幸太郎へのリスペクトも感じるのでご安心を)
ざっくり言うと自分が考えている事を他人に口にさせる事ができる「腹話術」の能力を使って、魔王・犬養と戦うという話。何を隠そう、僕はこの「ちっぽけな力を使って巨悪を倒す」と言う構図があまりにも大好きだ。この作品ではこの腹話術の能力が強化されてすごい力になったりもしないし、超人的な身体能力とかも出てこない。ただ普通の人間が、少しばかりの異能を使って戦い抜いていく。
練り込まれたストーリーのクオリティに圧倒される隠れた名作。
望月峯太郎『ドラゴンヘッド』:10巻
いわゆる終末もの。富士山の噴火によって崩壊した日本を描いた作品。終わり方に賛否両論あるけれども、極限状態での人間の狂気や恐怖、生への渇望といったテーマを描いた作品の原点のような作品だと思っている。20年前の作品でありながら、未だに読まれているところがそれを証明してるよね。
とにかく人間の姿をリアルに描き切っていて、最近広告とかでよく見る「王様ゲーム」とか「人狼」とかの恐怖心や猜疑心を描くような漫画はちゃんと古典としてこの作品読んで出直した方がいいと思うよ本当。
新川直司『四月は君の嘘』:11巻
何回読んでも泣いちゃうんだよなこれ。
一度はピアノを捨てた機械仕掛けのようなピアニストと、全てをぶっ壊すとんでもバイオリニストの出会いと別れの話。最終巻でタイトルの意味がわかるのだけれども、今こうしてこの文章を描いているだけで泣きそうになる。
演奏シーンの描写が半端なくて、臨場感と迫力がとんでもない。終盤の演奏シーンは毎回鳥肌モノですよ。
押見修造『惡の華』:11巻
押見修造の十八番であるドロドログチャグチャのジュブナイルもの。なのにさっぱりとした読後感がめちゃめちゃ好きなのだよ。中学編、高校編の2部に別れていて、個人的には2部が好き、というか大好き。クセは強いし難解な部分はあるけれども、思春期のモヤモヤとした感情をフィルターとか通さずそのまま紙の上で表現するとそりゃこういう作品になるよなという気持ち。
どこか村上龍『限りなく透明に近いブルー』と似ている。
星野泰視『デラシネマ』:8巻
戦後の日本映画を題材とした作品。主人公は舞台俳優と監督の2人で、彼らの映画に対する姿勢がとにかくアツい良作。中でも秀逸なのはキャラクターの描き方。敵も味方も、誰一人おろそかにする事なく、正しさを持った一面を描いていて、やり甲斐やお金、プライドや情熱といったそれぞれの側面でヒリつくようなアツさを見せてくれるのが大好きだった。
打ち切りではあるものの比較的綺麗にまとまっていて、コンパクトに読める名作。
三部けい『僕だけがいない街』:8巻
設定と構成と伏線があまりにも秀逸なミステリー作品。タイムリープとミステリーがかなり高い次元でミックスされていて、いろんな軸で物語が進んでいくそのダイナミクスがとんでもない。手に汗握る展開と秀逸な筆致で、気が付くと8巻読み終えている事がしばしば。何回読んでも伏線の回収の仕方に脱帽だ。
安野モヨコ『シュガシュガルーン』:8巻
こんなにキラキラした漫画他には無い。キャラクターも、アイテムも、街並みも、とにかく全てがキラキラしていて、少年漫画じゃあ絶対にお目にかかれないとんでもない世界観なのだ。僕は男だがこの漫画の世界観がとにかく好きすぎて、今まで何回読み返したかわからない。
ショコラの可愛さとピエールのかっこよさは異常。男子はこれ読むとちょっとモテるんじゃ無いかな、知らんけど。
10巻完結が面白い!
10巻完結ってだけでちょっと名作感ありますもんね。
[nlink url=”https://hannbunnko.com/archives/1750″]