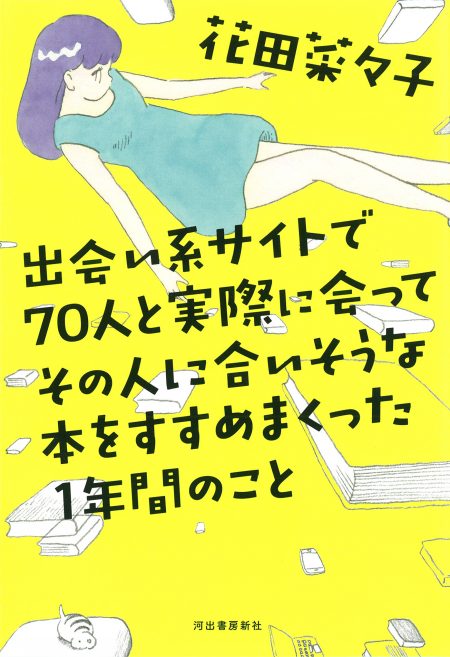小袋成彬は表現者だ。そして彼の1stアルバム『分離派の夏』はただただひたすらに美しい。
自身の内側にある言葉を内臓ごとひっくり返し、露悪的とすら言えるエピソードをこの上なく美しいメロディで歌いあげる。それを支えているのは彼の内面世界を表現し得る類い稀な歌唱力であり、聴くものを圧倒するその悪魔的な美しさには思わず胸が締め付けられるようだ。
宇多田ヒカルをもってして「この人の声を世に送り出す手助けをしなきゃいけない」と言わしめる不世出の才媛。その1stアルバム『分離派の夏』は、ちょっととんでもない。一周聴くのに体力を要するような超高密度の音楽、だけれどもその美しさに魅了されてしまった僕らはこの音楽から耳を離すことができない。
恐ろしいほどのクオリティのボーカルと、多層的に織り成されたサウンド。純文を彷彿とさせる美しい言葉の運びと、それと裏腹に極めて私的なエピソード達。これら全てを文字に起こそうだなんて土台無理な話ではあるのだけれども、このアルバムを聴いてレビューを書かないというのは、どうも僕には考えられない。
このレビューを通して
何よりまず始めに、この曲に関して言及しておかねばなるまい。
アルバム通して至極の名曲揃いのこのアルバムだが、リード曲である『Selfish』はやはり格別。特にこの歌詞はこのアルバム通じてのパンチラインであり、決して無視しては通れない部分だ。
時代に華を添えたくて 筆をとっていた訳じゃない
もう君は 分からなくていい
『Selfish』というタイトルが象徴するように、彼の音楽は人に聞かせる音楽ではなく、彼自身の内面から溢れ出る感情を音楽という形でアウトプットしたような、極めて内生的な音楽だ。内面世界へのダイブを繰り返し、より深くにある感情や言葉を汲み取るようにしてようやく作られた一つの結晶。それが『分離派の夏』だ。
そしてこのアルバム、彼自身がそこに目を向けていない分、やはり大衆に広く聴かれるような音楽ではない。
親しい友人のエピソードをモノローグ・インタリュード的に挿入した1・6曲目の語りにもあるように、芸術家として作品を作ることへの必然性、義務感。そこに突き動かされて作られたのがこの『分離派の夏』であり、彼自身は人に聴かれる事を意識してはいない。
だが、1リスナーとして、やはりこのアルバムは聴かれるべきだと思うのだ。
売れるものと売れて欲しいものが必ずしも一致しない現代のシーンにおいて、このアルバムが売れないのは、もはや必然といっても過言ではない。
しかし、多方面で絶賛の声があがり、「宇多田ヒカル」という強力なバックアップを持ち、事実素晴らしい音楽を作り上げた小袋成彬という人物。『分離派の夏』以前・以降と語られるような不朽の名盤に、歴史の分岐点に、このアルバムはなってもおかしくない、なるべきなのだ。
音楽好きが絶賛するだけでは足りない。まだこのアルバムを聴いていない全ての人が、このアルバムを聴く一助になれればと思いながらこの文章を書いている。
極めて日本的なR&B
このアルバム、R&Bとして全体にFrank Ocean『Blonde』に通ずるアンビエントさを持ち合わせながらも、その響きは圧倒的に日本語に寄せて作られている。
そして、今の日本でこれ以上に美しい日本語の歌は無いように思う。
楽曲において歌詞が担う役割に目を向けてみると、「ロックやポップスにおける歌詞の役割」と「R&Bやヒップホップにおける歌詞の役割」には決定的な隔たりがある。誤解を恐れずにざっくりと語ってしまえば、両者の一番の違いはリズムの必要性だろう。
ロックやポップスと比べてボーカルの自由度が高いR&Bやヒップホップの場合、歌には流麗なリズムが求められる。スムースな音階の移行、音節のコントロール、耳あたりの良いワードチョイス。特にそれは英語において顕著で、音節や発音の自由度の高い言語である英語の場合、究極に耳あたりのよいボーカルを追求する事でR&Bというジャンルが完成すると言っても過言ではない。
しかし、小袋本人も語っている通り、英語と日本語とは決定的に違う。
日本語の持つ独特の響き・リズム・音の構成、それらをR&Bという音楽に落とし込もうとした時、英語で歌われるようなR&Bを目指したところで限界がある。感覚的な言い方をしてしまえば、英語は丸いが日本語は四角く角が立っているので、英語のように輪郭がぼんやりとした響きにはならないのだ。
そしてこのアルバムにおいて彼は、その違いを強かに受け止めた上で、日本語でR&Bを歌うことに固執している。発音にしたって英語の響きに寄せているようなきらいは一切なく、むしろ日本語としてこの上なくはっきりとした発声が意識されている。一音一音がくっきりと、まるで語りかけるように歌い上げられ、僕らの耳に聞き慣れた日本語詞はダイレクトに僕らに響く。
つまるところ、小袋がこのアルバムで示したのは、Frank OceanやJames Blakeといった列強勢の音楽を下敷きに作り上げられた、新しい国産R&Bの姿だと言っても良い。
私的な歌詞と文芸性
友人の死、失恋、妹の結婚。彼の曲で描かれるのは極めてリアルな実体験に基づくエピソードであり、アーティストとしての表現はあくまで内生的だ。極めてプライベートなエピソードと、私小説のように内面を抉り出す歌詞。そこにはヒリつくような迫力があり、音楽的な静けさとは対比的に実に生々しく、時には泥臭くすらある。この泥臭さなんて、もはやR&Bというよりもフォークのそれだろう。
言葉は真実を映さない
君は気付いてしまったみたいだ
この世は全てがフィクション
– 『E.Primavesi』
本人も曲中で歌っている通り、歌詞が必ずしも等身大の真実とは限らない。そこには、極めて私的な体験を楽曲に落とし込む内に加えられた、ある種自然な誇張や脚色が存在する。ただし、それはあくまで芸術家としての小袋の脚色である。それが無ければこのアルバムは実に泥臭く、あまりに直接的な表現はそこらのJ-POPと変わらないような陳腐さで片付けられていたことだろう。
文芸的とすら称される彼の詞、その一例を引用する。
呼び出されたのは夜の1時
いつもは寂れた南の飲み屋なのに
たまにしか飲まない緑色のテキーラに
雨の渋谷に会話は要らない
– 『E.Primavesi』
喘息をこらえて 縁側の座椅子で 朝まで話そう
先行漂うリビング
僕らを睨む君の親父の遺影
陽炎に僕らは溶けた
– 『Daydream in Guam』
借りた車のシートを倒し
波打つ肌を迎えたコインパークの隅
花火の光を隠した夜も
– 『夏の夢』
かける言葉は特に無い
まあ元気でいて欲しい
深い愛の物語には 栞をつけましょう
– 『門出』
色彩や情景、感情と描写、口語と文章、リアルとフィクション。それらがシームレスに入り混じって歌詞の中に高低差をつけているものの、決して散文には振り切れない。そして何より単語の一つ一つが世界観に凹凸をもたらしている感覚が美しい。誰のものでもない自分自身の感情をストレートに歌い上げる彼の歌が文芸的な美しさを持ち合わせているのは、ひとえに彼の作詞センスに依るものだろう。
随一の歌唱力
緩急自在に音階の海を自由自在に泳ぎ回る歌唱力、自身の詩世界を表現しきる表現力、天性の柔らかい歌声。ファルセットを多用しながら高めのキーで歌うその歌声はある種女性的ですらあり、一人称の「俺」という言葉との落差もまた美しい。
先日生放送で歌う彼の映像を観た。
信じられない事に、彼の歌はライブで聴いた方が素晴らしい。
音源からも彼の歌唱力については疑う余地はないのだが、歌声をレビューする、という意味ではやはりライブを観ない事には始まらない。幸い夏にはフジロックの出演が決まっているし、既にこの時点で僕は彼の音楽の魅力に関して十分に語っている。彼のボーカルに関しては夏、ライブを観てからでも遅くないだろう。
シーンの分岐点
例えばTravisの2ndアルバム『The Man Who』がブリットポップの終焉と共に、後のUKロックに色濃い影響を与えた様に。
例えば2016年にリリースされたFrank Ocean『Blonde』。度々アンビエントR&Bと称される彼の音楽が、R&Bの歴史に新たなページを刻んだ様に。
例えばYogee New Wavesの大名曲『CLIMAX NIGHT』が昨今の日本インディーシーンを一変させた様に。
小袋成彬『分離派の夏』も、現代のシーンにおける一つの分岐点となり得ると、僕は信じて疑わない。