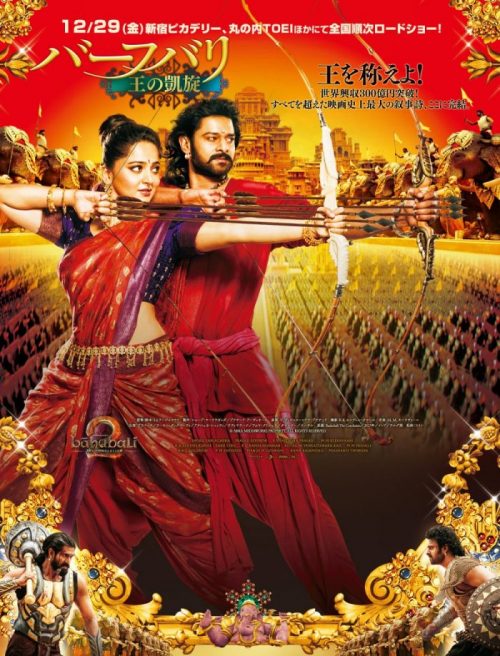踊ってばかりの国、というバンドが大好きだ。
正確に言えば大好きだった。
そして今、再び大好きなバンドの一つになった。
メンバー変更を経て完成された現在の踊ってばかりの国の新曲『サイクリングロード』『メロディ』の話をしようじゃないか。
4人編成時代
踊ってばかりの国、と聞いて真っ先に僕がイメージするのは『話はない』『言葉も出ない』『!!!』『SEBULBA』『東京』あたりの初期の曲だ。
尖ったワードチョイスに挑発的な歌詞、それと相反するように美しいメロディと轟音。退廃的な詩世界と暴力的とすら言える美しさと音で組み立てられた、日本にしか生まれ得ない音楽。それが僕の好きだった踊ってばかりの国の音楽だ。
3年ほど前に新代田FEVERで観た彼らのライブを、僕は一生忘れない。
当時は4人編成。既に脱退してしまったDr.佐藤とGt.林がいた時代だ。結果的にその4人体制でのライブを目撃できたのはその時一度きりなのだけれども、あれは当時の僕にとっては完全に事件だった。
重たく、けれどこの上なく正確で鋭いドラム。ライブハウスを溺れるような轟音で埋め尽くすギターとベース。そして下津の狂気じみた歌声と迫力。そのあり方は破壊的でありながら耽美的。高密度の音の洪水のような音楽性はもはやシューゲイザーのそれであった。そこに下津の天性のサイケ感と狂気が加わってそのサウンドは唯一無二。そしてライブは完璧に完成されていて、今までずっと音源で聞いていた踊ってばかりの国というバンドとは全く違う、本物の『踊ってばかりの国』だった。
だからこそ、そのサウンドの根幹を成していたDr.佐藤とGt.林の脱退は僕を大いに落胆させた。
5人で迎える新体制
Dr.佐藤の脱退後、THE 米騒動の坂本が加入し、Gt.林の後釜には元ドレスコーズの丸山が収まった。さらにはそこにGt.大久保仁が加入して5人体制となったのが昨年の事。
ところがこの5人体制、言葉を隠さずに言ってしまえばあまりよろしくなかった。
前述の林と佐藤の二人というのは日本でもトップレベルのプレイヤーであり、その二人が抜けた穴を容易に埋められる訳もなく、当時のライブは以前との差に落胆を禁じ得なかった。
佐藤の脱退後にリリースされた『しゃくなげ』『Boy』あたりの曲を聞いても、新体制でのライブ映像を観ても、下津の天才的なソングライティングとカリスマによって漸く保っているという感覚がどうしても拭えず、段々と僕の耳は彼らから離れて行ってしまった訳だ。
ところが僕は再びその度肝を『踊ってばかりの国』に抜かれる事になる。
『サイクリングロード』&『メロディ』
まずは『サイクリングロード』
轟音シューゲのイメージを完璧に脱ぎ去り、海外インディーの様な軽さと心地よさが春にぴったりなこの曲。下津のボーカルも軽妙でポップでありながらどことなくサイケで不安定な雰囲気も残っているバランス感が最高なのだ。
そして『メロディー』
『サイクリングロード』同様、ポップさと軽さを備え、爽やかな疾走感溢れるこの曲。驚く事に「生きる歓び」みたいなものが歌われていて、これまでの破壊的で退廃的な詩世界とは全く違う、どこか牧歌的とすら思える歌詞。
そばにおいで 生きててもいいのよ
全ての命とメロディよ
生まれてきて良かったと思える
そんな日に歌うメロディよ メロディよ
この曲を聞いた時、「踊ってばかりは変わった」という事実がストンと胸に落ちる感覚があったのだ。
以前の踊ってばかりの国が良かったという事実はもちろん変わらない。だがそれに拘るあまり、現体制の彼らの音楽を頭ごなしに否定していた様な部分があった、あってしまったと言うべきか。それがこの2曲を聞いて、心の底から今の彼らの音楽を「踊ってばかりの国の音楽」だと思えたのだ。また心の底から彼らの音楽を愛して、彼らの音楽に救われる、勇気付けられる日々が過ごせるのだ。こんなに嬉しい事もないだろう。
現在のシーンの立役者
そして僕が一つ言っておきたいのは、踊ってばかりの国というバンドが現代のシーンにもたらした影響だ。
邦楽に多少明るい人であれば、Yogee New Wavesやnever young beachを知らない人はいないだろう。そんな彼らが活躍するここ数年間のシーンの土壌を作ったのは、間違いなく踊ってばかりの国だ。
『CLIMAX NIGHT』のもつサイケでポップで耳に染み付く感覚とVo.角館のゆったりと歌謡曲の様なボーカル。
→2017年インディー界のトップランナー、Yogee New Waves『WAVES』を聴いたか
ネバヤン阿部ちゃんの、ゆったりとコブシの効いた歌い回し。
→梅雨明けと同時リリース。never young beach『A GOOD TIEM』がこの夏を彩る!
どうしても長くなりそうなので手短に語るが、時代の担い手といえる様なバンドが存在しなかった2012年前後。その強烈な個性と天性のボーカルでシーンに現れた下津光史と言うカリスマが、後のバンドに与えた影響が大きいのは想像に難くない。サウンド面だけではなく、バンドとしての在り方やスタンスに対して、と言う意味でも。
そしてやっぱり、下北沢という街はこれらのカルチャーの中心であった様な気がしてならない。安酒、バンド、古着、ストリート、曽我部恵一。下北で日付が変わるくらいまで飲んだりしていると、たまに下津を見かけることがあった。だいぶ酔っ払った様子で、ご機嫌に鼻唄なんか歌いながら歩いている姿をよく覚えている。その姿はステレオタイプなバンドマンと言う感じがあって(尊敬できない点も多いけれども)やはりどこかかっこいいなと思ったものだ。
おわりに
日本のリアルなサイケ。手放しで美しいって思っていいのかなっていう気持ちを少し持ちながら、やっぱり美しいって感じてしまう。で、戸惑いを含めて、そう思わせてくれうところが美しいんじゃないかなと思うなぁ。 via 踊ってばかりの国『メロディ』Music Video (2018) https://t.co/TERsMBVWyF
— Gotch (@gotch_akg) 2018年4月13日
アジカン後藤にこうまで言わせる今の彼らの音楽性。
来週4月18日にリリースされる彼らのアルバム『君のために生きていくね』が楽しみでならない。